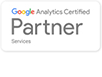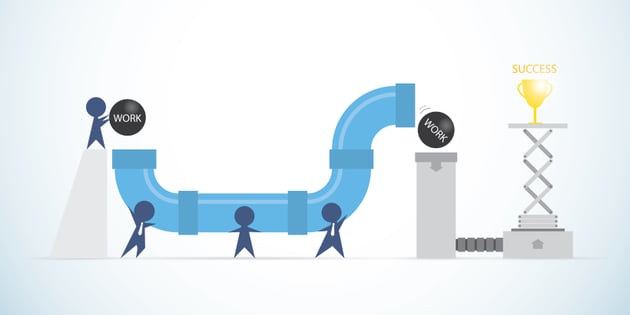
「マーケティングにおけるパイプラインとは?」
「パイプラインマーケティングは、BtoBマーケティングで有効?」
BtoB企業のマーケティング担当者の中には、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
ビジネスにおいては、主に営業(セールス)で使われる「パイプライン」という用語ですが、マーケティングにおいても、「デマンドジェネレーションや、リードジェネレーションを進化させた施策」の意味として使うことがあります。
本記事では、営業(セールス)における「パイプライン」と、マーケティングにおける「パイプライン」の意味の違いや、BtoBマーケティングで有効なパイプラインの考え方を解説します。
目次
パイプラインとは?
ビジネスにおいて「パイプライン」とは、営業(セールス)担当者が見込み客を顧客へ転換する一連のプロセスを時系列で表したものです。例えば、「見込み客への、アプローチ→ヒアリング→提案→見積もりの提示→受注」といった流れがパイプラインと呼ばれます。
パイプラインとマーケティングファネルの違い
パイプラインと混同されやすい用語として、マーケティングファネルがあります。マーケティングファネルは、見込み客の購買プロセスを可視化したもので、一般的に「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購買」の4つで表されます。マーケティングファネルが見込み客の視点で表現されているのに対し、パイプラインは自社の営業(セールス)担当者の視点で表現される点が異なります。
マーケティングファネルについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
「マーケティングファネルとは?BtoBに重要な理由とメリット・デメリットを解説」
次項では、従来の意味合いで営業(セールス)担当者向けのパイプラインに触れたあと、マーケティング担当者向けのパイプラインについても解説します。
パイプライン管理とは?
パイプライン管理とは、上述したような一連のプロセスを可視化し、分析や改善を行っていくマネジメント手法のことです。ここでは、パイプライン管理が普及した背景と、具体的な内容について解説します。
パイプライン管理がBtoBの営業活動で使われるようになった背景
従来の営業活動では、プロセスを管理する考え方が浸透していなかったため、どの案件がどこまで進んでいるか、担当者以外は把握できていませんでした。また、ノウハウが共有されることが少なく、個人の能力によって成果に差が出ることも課題でした。
そこで登場したのが、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)といったツールです。SFAは、獲得した見込み客の属性情報や、営業活動の履歴を蓄積・可視化し、チーム全体での共有を可能にします。CRMは、顧客の基本情報や問い合わせ・取引の履歴を管理します。
これらのツールによって、営業活動をプロセスに分けて可視化するメリットが知られるようになり、パイプライン管理が普及しました。
パイプライン管理で行うこと
パイプライン管理では、次のような目標や仮説を時系列に並べて、売上管理を行います。
- 目標売上額の達成に必要な見込み客数は、確保できているか?
- 売り上げは、「いつ」「どの程度上がる」見込みか?
- 受注に至るまでのアプローチに、どれくらいの時間がかかるか?
などの目標や仮説を、時系列に並べて、売上管理を行います。
さらに、上記の売上管理に加えて、プロセスのボトルネックを見つけ、改善を行っていくこともパイプライン管理の範疇となります。
例えば、
- 問い合わせ
- ヒアリング
- 提案
- 見積もり書の提示
- 先方社内稟議
- 受注
など、プロセスを細かく分け改善点をあぶりだすことで、営業力の改善が可能です。
パイプライン管理を実践するためのステップを紹介
営業(セールス)担当者におけるパイプライン管理を成功させるためには、正しい手順を把握しておかなければなりません。ここでは、パイプライン管理を実践するときに必要な3つのステップを解説します。
1.営業プロセスを細分化する
はじめのステップは、営業プロセスの細分化です。上述したように、お問い合わせやヒアリング、初訪問など、初回アポから契約までの営業プロセスを細かく分けていきます。その際、顧客の行動を軸に考えることで、契約までの営業プロセスは細分化しやすくなります。
ただし、営業プロセスの細分化のしすぎには注意が必要です。詳しくは、このあとの「パイプライン管理の注意点」で説明します。
2.営業プロセスを進めるためのアクションを明確にする
営業プロセスを細分化したあとは、細分化した各プロセスを進めるためのアクションを明確にしなければなりません。
例えば、問い合わせからアポイントに移る場合は、「電話またはメールで担当者とヒアリング」のようなアクションプランが考えられます。提案から見積もり書の提示までの営業プロセスであれば、「導入メリットを伝えるために、シミュレーションを提示する」のようなアクションプランが考えられるでしょう。アクションプランを考える際は、営業(セールス)担当者がより効率的に動けるように、数字や役職、顧客の行動なども具体的に決めておくことがポイントです。
アクションプランを明確にすることで、営業(セールス)担当者は迷うことなく、次のステップまでの行動を実行に移すことができ、営業活動の生産性を高められます。
3.細分化した各プロセスの社数と転換率を可視化する
3つ目のステップは、細分化した各プロセスの社数と転換率の可視化です。
例えば、
・問い合わせ(100社/月)
↓90%
・ヒアリング(90社/月)
↓89%
・提案(80社/月)
↓63%
・見積もり書の提示(50社/月)
↓40%
・先方社内稟議(20社/月)
↓25%
・受注(5社/月)
のように、細分化した各プロセスとその転換率を可視化します。社数と転換率を可視化しデータとして蓄積していくことで、全体の流れでボトルネックとなっているプロセスの発見が可能です。
パイプライン管理のメリット
パイプライン管理を実践するためのステップについて紹介してきました。ここでは、実践した場合のメリットを2つ紹介します。
ボトルネックの発見
前項で解説したように、プロセスごとの転換率を可視化してボトルネックを発見できるため、
- 転換率の悪いプロセスを見直そう
- 先月より受注が落ちた、〇〇の転換率が悪いようだ
などのように、改善策や課題が見つかり、PDCAを回していくことができます。
また、ボトルネックを把握することで、営業(セールス)担当者それぞれに対して、データにもとづいた客観的なアドバイスを行えます。
マーケティング活動への活用
受注につながりやすい見込み客や流入経路を把握し、費用対効果の高い施策にマーケティングのリソースを集中させられるようになります。
パイプライン管理の注意点
続いて、パイプライン管理を実践する上での注意点を2つ紹介します。
プロセスを細かくしすぎない
営業プロセスを細かく分けすぎると、些細なことに気を取られてしまい、本質的な課題を見つけられない恐れがあります。どの部分に課題があるのかを把握するためにも、細分化は客観的で、正確な全体像がとらえられる程度にとどめておきましょう。
リアルタイムかつ正確な進捗把握が必要
セールスにおけるパイプライン管理では、細分化した各プロセスの進捗をリアルタイムかつ正確に把握する必要があります。エクセルやスプレッドシートでの管理も可能ではありますが、情報が正確でない場合や、リアルタイム性に乏しい場合は、パイプライン管理のメリットを十分に得られないので注意しましょう。
パイプライン管理は、SFAとCRMで効率化
上述したように、パイプライン管理を実施するために欠かせないのが、正確かつリアルタイムな進捗把握です。効率的に行うには、SFAツールやCRMツールなどの利用を検討する必要があります。
SFAツールを用いれば、
- 各営業担当の入力による、リアルタイム管理
- 全スタッフが専用画面を用いての、状況確認
- ダッシュボードの活用で、課題の明確化
などが可能になります。
また、CRMツールの中にも、営業活動のデータを登録して進捗を管理できるものがあり、パイプライン管理に活用できます。例えば、「HubSpot CRM」は、パイプライン管理に適した機能を持つ無料のCRMツールです。これからCRMツールを導入しようとしている企業には、特におすすめです。
HubSpot CRMについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
「HubSpotとは何か?機能や使い方、導入方法を徹底解説!」
パイプライン管理の手順を理解し、SFAやCRMなどのツールを活用することで、より効率的なセールスが可能です。
HubSpot CRM以外にも、パイプライン管理に適しているツールは以下のものがあります。
パイプライン管理に適しているCRM、SFAツール
Salesforce(セールスフォース)
CRM(顧客関係管理)ソフトウェアの大手企業であり、営業パイプライン管理に特化したツールを提供しています。営業活動の段階ごとに顧客データを追跡し、見込み客(リード)から契約締結までの進捗を管理することができます。
Zoho CRM(ゾーホー CRM)
クラウドベースのCRMソフトウェアであり、営業活動の効率化とパイプラインの可視化に重点を置いています。見込み客の管理、商談の進捗管理、予測分析などの機能があります。
Pipedrive(パイプドライブ)
中小企業向けのCRMソフトウェアであり、営業活動のパイプライン管理に特化しています。見込み客の追跡、商談の進捗管理、タスクの割り当てなどの機能があります。
Microsoft Dynamics 365 Sales(マイクロソフト ダイナミクス 365 セールス)
マイクロソフトのCRMおよび営業自動化ソリューションであり、パイプライン管理に役立つツールを提供しています。営業プロセスの可視化、商談の追跡、顧客インサイトの分析などが可能です。
マーケティングパイプラインとセールスパイプライン
ここまでは、営業(セールス)担当者が対象となる通常のパイプラインの説明を行ってきました。ここからは、「マーケティング担当者を対象としたパイプライン」について、解説します。
上述したように、ビジネスにおける「パイプライン」とは、営業(セールス)担当者が辿る一連のプロセスを指すのが一般的です。しかし、近年ではMA(マーケティングオートメーション)が普及したこともあり、マーケティングでのプロセスを「パイプライン」と呼ぶことも増えてきました。
両者を区別するために、営業でのパイプラインのことは「セールスパイプライン」、マーケティングでのパイプラインは「マーケティングパイプライン」と呼称します。
では、マーケティングにおける「パイプライン」とは、どのようなプロセスを指すのでしょうか。マーケティングでのパイプライン、「マーケティングパイプライン」とは、俗にいう「デマンドジェネレーション」のことです。
デマンドジェネレーションとは、
の3つのプロセスをまとめた一連の流れのことで、営業部門へ渡す前の見込み客の創出活動全般のことを指します。BtoBマーケティングの中でも、特に重要で奥が深いプロセスです。
一方で、本記事の前半で紹介した「セールスパイプライン」とは、マーケティングにより創出された見込み客への、最初のアプローチから受注に至るまでのプロセスのことです。
ビジネスでは、マーケティングパイプラインで創出した見込み客を、セールスパイプラインに渡し、セールスパイプラインで失注した見込み客を、再度マーケティングパイプラインでフォローする。といった流れで、プロセスを回していきます。
パイプラインマーケティングとは
マーケティングの「パイプライン」とは、リードジェネレーションからリードクオリフィケーションまでをまとめた、「デマンドジェネレーション」のことを指しますが、それとは別に、「パイプラインマーケティング」という用語も存在します。
パイプラインマーケティングを端的に述べると、リードジェネレーション施策をさらに進化させたものです。パイプラインマーケティングでは、認知から購買に至るプロセスを俯瞰し、収益を創出する最終段階のプロセスをもとに、見込み客獲得のためのあらゆるマーケティング施策を最適化します。
ビジネスにおいて一番注力すべきは、収益の向上です。しかし、マーケティングでは、リード獲得数にこだわるあまり、収益の向上ではなく、直接CVであるリード獲得単価を重視してしまうケースも少なくありません。リード獲得単価(直接CV)だけに注力してしまうと、本来の目的である収益機会を逃す恐れがあります。
そこで、パイプラインマーケティングを実践し、見込み客獲得のためのあらゆるマーケティング施策を最適化していくことができれば、収益向上の機会を逃すという損失を回避することが可能です。
では、パイプラインマーケティングでは、具体的に、どのような施策を実践するのでしょうか。
認知から購買までのプロセスを俯瞰するパイプラインマーケティングでは、「アトリビューション」という手法を用います。アトリビューションとは、得られた収益を、顧客が認知から購買までに触れてきた各マーケティング施策へ分配し、各施策の貢献度を図る手法です。
アトリビューションを用いることで、「直接CV」だけではなく、CVするために貢献してくれた「間接CV」も考慮して、広告の評価を行えるようになります。
アトリビューション手法をリードジェネレーションにあてはめた場合、貢献度を測る各施策となるのは、リスティング広告やSNS広告などです。
例えば、直接CVがリスティング広告だったとしても、顧客が前段階でSNS広告をクリックしていれば、SNS広告は間接的にCVへの貢献をしてくれていることがわかります。
アトリビューションを活用すれば、顧客がこれまでに触れた施策とその貢献度を把握でき、最終的な収益の計測が可能です。
アトリビューションを用いて、各施策の貢献度を把握し、どの施策に費用を投資すべきかを判断できれば、マーケティングの効率化と収益の向上が見込めます。
BtoBマーケティングは、顧客が商品やサービスを認知し、受注に至るまでの期間が長いのが特長です。そのため、顧客が認知から購買に至るまでに触れる施策が、多数になることが想定されます。その中で、正しく各施策の効果や貢献度を理解していくパイプラインマーケティングは、BtoBマーケティングに向いている手法といえるのです。
まとめ
セールスだけではなく、マーケティングでも使われる「パイプライン」という用語ですが、マーケティングにおいての「パイプライン」とは、デマンドジェネレーションの一連の流れを指し、「パイプラインマーケティング」とは、リードジェネレーションをさらに進化させた施策のことを指します。
パイプラインマーケティングを効率的に実施するためには、各施策の貢献度を測る「アトリビューション」が欠かせません。アトリビューション手法を用いて、正しく施策の効果を理解し、適切な予算を分配することで、収益の最大化が狙えます。
メディックスでは、本記事で解説したパイプラインマーケティングで必要となるアトリビューション分析の解析を提供しています。また、リードジェネレーションでは、リスティング広告からペイドメディアまで、幅広い施策の提案が可能です。SNS広告では、豊富なユーザデータを活用した様々なターゲティングが行えます。
BtoBマーケティングについて、何か困りごとがある際は、お気軽にご相談ください。